-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
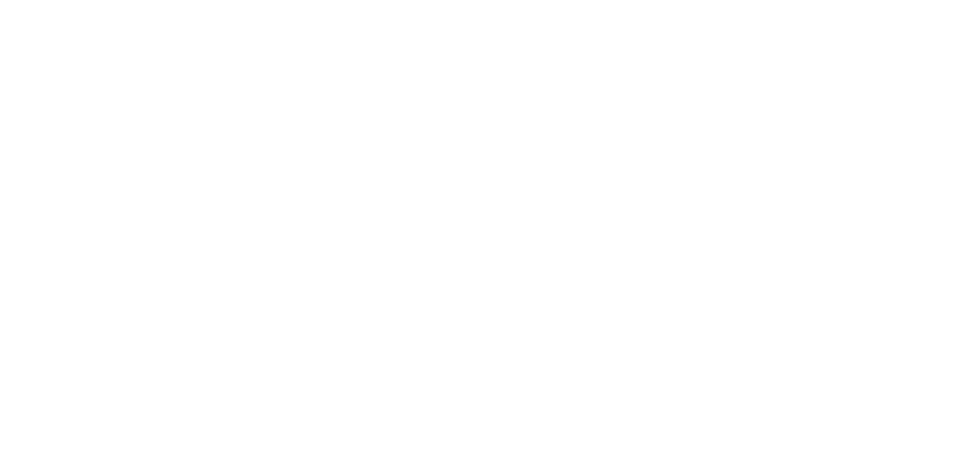
皆さんこんにちは!
折敷瀬クレーン、更新担当の中西です!
クレーン工事は今、大きな転換期を迎えている。
建設業の労働力不足と安全意識の高まりを背景に、ICT・自動制御・遠隔管理が導入され、現場の在り方そのものが変わりつつある。
近年の油圧クレーンには、ブーム角度・荷重・風速を自動計測し、リアルタイムで安全範囲を表示する「作業範囲制限装置」が標準装備されている。
また、GPSやIMU(慣性センサー)を用いた位置制御技術により、ミリ単位での吊荷位置決めが可能になっている。
将来的には、AIによる自動吊荷制御や無人運転の実証も進む見込みだ。
BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)によって、クレーン配置・吊荷動線を三次元で可視化できるようになった。
これにより、干渉チェック・吊荷シミュレーション・重機選定が事前に最適化され、現場でのリスクが大幅に低減されている。
デジタル化が進む一方で、技能継承の重要性は変わらない。
クレーン操作は経験による感覚的判断が求められる領域が多く、ベテランから若手への知識共有が不可欠である。
遠隔教育・シミュレーター訓練・VR現場体験といった新しい教育手法が増え、技能伝承の形も進化している。
大型クレーンの移動・設置には多大なエネルギーが必要である。
電動化・ハイブリッド化・軽量設計による燃料削減や、低騒音・低振動機種の普及が進んでおり、環境対応も技術課題の一つである。
また、災害復旧やインフラ更新現場では、クレーンの機動力が社会インフラを守る要となっている。
クレーン工事は「人の技」から「人と機械の協働」へと進化している。
しかし、どれほど機械が進化しても、現場の安全を守るのは人の判断である。
技術革新と安全文化の両立こそが、これからのクレーン工事のテーマである。

皆さんこんにちは!
折敷瀬クレーン、更新担当の中西です!
クレーン工事における安全管理は、「当たり前」をどれだけ徹底できるかにかかっている。
安全対策は法律で義務付けられているが、形式的な遵守では不十分であり、現場の実践と意識が伴って初めて効果を発揮する。
作業開始前には必ず「KY(危険予知)ミーティング」を実施する。
当日の作業内容・吊荷重量・風速・地盤状態・周囲環境を共有し、リスクの洗い出しと対策を明文化する。
特に注意すべきは以下の点である。
強風(風速10m/s以上)での中止判断
電線・高圧線との距離(最低2m以上の離隔)
人通り・車両動線の確保
吊荷の下に人を入れない
安全とは「止める勇気」である。時間や納期よりも命を優先する文化を根付かせなければならない。
クレーン本体の整備不良は重大事故につながる。
作業前には、ブーム・ワイヤ・フック・アウトリガー・油圧系統を点検し、異音・油漏れ・変形がないか確認する。
特にワイヤの素線切れやドラム摩耗は、吊荷落下事故の主要因となる。
オペレーターは国家資格(移動式クレーン運転士)を持つことが前提であり、定期教育で最新知識を維持する。
合図者はクレーン作業の司令塔である。
合図の統一がされていない現場では、誤操作が起こりやすい。
手信号・無線・トランシーバーなどを使う場合でも、指示系統は一本化する。
「誰が指揮者か」「誰が玉掛けか」を明確にすることで混乱を防ぐ。
クレーン工事は単独では成立しない。建設現場では他業種との同時作業が多く、作業範囲の重複が危険を生む。
隣接作業班との調整や立入制限区画の明示、搬入経路の整備など、全体調整が安全施工の基盤である。

皆さんこんにちは!
折敷瀬クレーン、更新担当の中西です!
吊り上げ作業の核心は、荷重とバランスの制御である。
クレーン工事において、重量計算・重心把握・吊点設計を誤ると、どんな高性能機でも一瞬で事故に至る。ここでは「吊り計画」と「荷重計算」の基本を整理する。
吊り計画とは、吊り上げ対象物を安全に所定位置へ移動するための設計図である。
単に吊る位置を決めるだけでなく、下記の要素を全て数値化・図面化する。
吊荷重量と重心位置
クレーンブーム角度・作業半径
アウトリガー反力と地耐力
ワイヤスリングの角度と許容荷重
玉掛け具の選定(シャックル・フック・スリングベルト等)
作業環境条件(風速・障害物・電線・周囲交通)
これらを一枚の施工計画書に落とし込み、全員が共有することで安全性が担保される。
クレーンの吊上げ能力は、作業半径が大きくなるほど低下する。
例えば、25tラフタークレーンでも、ブーム長やジブ角度次第で実際に吊れる重量は10t以下になることもある。
このため、吊荷+吊具+ワイヤ+回転モーメントを総合的に評価し、安全率(通常1.25〜1.5倍)を考慮して機種選定を行う。
また、ワイヤロープの許容荷重は「角度補正」が必要である。
吊角が60度を超えると張力が急増するため、角度はできる限り小さく取る設計が求められる。
重量物の吊りでは「重心を外す」ことが最も危険である。
鉄骨梁・機械設備などは、形状や内部構造により見た目の中心と重心が一致しない。
吊点位置を誤ると、吊り上げた瞬間に荷が傾き、玉掛け具が破断する恐れがある。
事前に図面や現物計測で重量配分を確認し、吊り試験で微調整することが鉄則である。
計算通りに吊れるとは限らない。現場では風向き・振動・地盤変位など動的要因が加わる。
だからこそ、経験を持つオペレーターの感覚と理論を融合させることが、安全施工の鍵となる。

皆さんこんにちは!
折敷瀬クレーン、更新担当の中西です!
クレーン工事は、単に重量物を吊り上げる作業ではない。現場全体の流れを左右する「吊りの設計」であり、安全・精度・効率を三位一体で成立させる総合技術である。
建設現場・プラント・橋梁・製造ラインなど、どの産業分野においても、重量物の据付・移設・撤去にはクレーンが欠かせない。だが、その運用には高度な計画力と現場判断が求められる。
クレーン工事は建築・設備・土木の補助作業ではなく、工程全体の進行を支配する「中核工種」である。
鉄骨建方・機械据付・プレキャスト施工など、上棟・組立・設置工程の要に位置し、他職種の段取りや搬入スケジュールを左右する。
そのため、施工計画段階での「クレーン配置計画図」「吊荷経路図」「地耐力確認書」の整備は必須であり、設計者・監督・オペレーターが三位一体で調整を行う必要がある。
代表的なクレーンには以下のようなものがある。
ラフタークレーン:小回りが利き、都市部や住宅現場に適する。アウトリガーを張り出して安定性を確保。
オールテレーンクレーン:高速走行と高出力を兼ね備えた大型機。橋梁・プラントなどの長距離搬入に対応。
クローラークレーン:履帯走行による抜群の安定性が特徴。地耐力が低い現場でも沈下しにくく、重量物の高所建方に強い。
トラッククレーン:汎用性が高く、機動力重視の小規模工事で活躍。
現場条件(スペース・地盤・重量・高さ・回転半径)によって最適機種を選定しなければならない。
吊作業で最も重要なのは、実際の吊り上げよりも「吊る前の段取り」である。
作業計画書では、吊荷重量・重心位置・ワイヤ角度・風速制限・地盤沈下防止策などを明確にし、想定外のリスクを排除する。
また、作業中の合図・通信手段・避難経路までを事前に確認する。
クレーンは“人が動かす巨大なテコ”であり、その一挙手一投足が命に直結する。
現場では、オペレーター・玉掛け者・合図者の三者が同じ認識で動くことが絶対条件だ。
クレーン工事の事故原因の多くは、ヒューマンエラーにある。
吊荷落下、接触、転倒、挟まれといった災害の背景には「合図不徹底」「重量過信」「地耐力不足」「強風時作業」などがある。
法令上も、クレーン等安全規則により、作業指揮者・合図者の選任、作業計画の策定、日常点検の実施が義務づけられている。
安全とは一過性の注意ではなく、現場文化として定着させるべき仕組みである。
